
当教室では、教室側で楽譜や教材を指定することもあれば、生徒さん自身で弾きたい楽譜を持ってきてもらう場合もあります。
先日、ある生徒さんに「弾きたい曲を持ってきてもよいですよ。最近は1曲づつ購入できるサイトもありますから」とお伝えしたら、
「見た目で曲の難易度が分からない」という話になりました。
そうですよね!
そのようなサイトには、大抵「初級」「中級」「上級」(もう少し細かい場合もあるが)位の分類しかありません。
サンプル画像があってもそれが難しいのか弾けそうなのか、もしかして簡単すぎるのか、パッと見わかりません。
経験が浅い生徒さんの場合であれば余計わからないでしょう。
正直言って、
実際に弾いてみないと分かりません!
ですが、楽譜を購入する前に実際に弾くことはなかなかできません。
そこで今回は、
当教室代表講師の長年の経験による
「楽譜の見た目だけで難易度を判断する方法」
をお伝えします。
もちろん、必ず当たるわけではありませんが、大きくははずさないと自負しています。
Contents
判断基準1:調号
楽譜の先頭にあるト音記号やヘ音記号の右隣にある♯(シャープ)や♭(フラット)の数を確認します。
(これらの記号を「調号」といいます)
鍵盤楽器の場合、大抵はシャープやフラットの数が多いほど難易度が高い
理由は、楽譜上の本来の音の高さより半音上げ下げしなければならない音が増えること、その結果白鍵よりも奥にあり横幅が狭い黒鍵をたくさん弾くことになるからです。
(白鍵・黒鍵の概念がないギターなどの場合はまた違うのかもしれませんが、ギターの経験がない私にはわかりません)
初心者や初級者には、調号の数が少ないものをおすすめします
中上級者位の経験があると、ご自身でフラットが好きシャープは苦手など好みができあがっていたりするので、好きに選んでいただいてよいです。
意外なのは、調号が5つや6つあるよりも、3つや4つ位の時の方が弾きづらい場合があります。
理由は、調号が5つや6つの場合は、ほぼ黒鍵ばかりを弾くことになりますが、3つや4つの場合は白鍵と黒鍵をほぼ同数弾くことになるので、指の移動を考えると地味に大変だったりします。
このあたりは個人の得手不得手によりますので、ご自身がどちらが得意かで判断してもよいでしょう。
あと忘れていけないのが、転調(曲の途中で調が変わること)
最初は調号が少なくても、途中から急に調号が増えることがあります。
原曲にボーカルが入っている曲の場合、サビや後半で半音上げになるケースが多く、その場合は急に調号が増える場合があります。
転調はオンラインサービスの場合、最後まで確認することが難しい場合がありますが、店頭に行ける場合は必ず確認しましょう。
その他、調号に関連してですが、調号の数に加え、臨時記号(曲の途中で出てくる♯や♭)が多い曲は難易度が上がります。その点もチェックしましょう。
判断基準2:楽譜の黒さと曲の速度
楽譜の黒さとは、
16分音符や32分音符、6連符など、細かい音符がたくさんあるかどうかです
これらの音符がたくさんある場合、楽譜が音符で埋まり、黒っぽくなります。よほど速弾きが得意な方でない限り、16分音符を見ただけで「難しい」と感じる方が多いでしょう。
一般的には、楽譜が黒っぽいほど難易度が上がります
しかし、楽譜が黒いからといって、必ずしも超絶技巧の曲とは限りません。
楽譜の黒さに加えて、曲の速度(テンポ)を確認してください
楽譜に細かい音符がたくさんあって真っ黒でも、テンポが遅い曲の場合、それほど怖がる必要がない場合も多いです。楽譜の黒さと曲の速度の両方を見て総合的に判断してください。
判断基準3:拍子の確認
何分の何拍子なのかを確認します。
大抵の方は4分の4拍子に一番慣れているかと思います。
4分の3拍子はポップスには少な目ですので、ノリが苦手な方はチャレンジするのか避けるのか判断しましょう。加えて4分の3拍子は速い曲が多めです。
その他、8分の9拍子や8分の12拍子など見慣れないものの場合、指導者がいる場合は教えてくれるかと思いますので、特別苦手意識がない場合はチャレンジしてもよいでしょう。
また、4分の5拍子、8分の5拍子、8分の7拍子など変拍子と呼ばれるものもあります。これらは数えれば大丈夫なのですが、上記に挙げた拍子で四苦八苦している場合は、次の機会に見送ったほうが良いかもしれません。
判断基準4:リズムが難しそうかどうか?
ポップスやジャズ、フュージョンなど、今どきのかっこいい系の曲には、シンコペーション(♪♩♪など)という、強拍と弱拍が逆転するリズムが多用されています。
シンコペーションの連続(それもタイでつながっている)は、見た目よりも難しい!
クラシックの上級の楽譜は真っ黒でいかにも難しそうですが、音階やアルペジオ(分散和音)が多用されていて、それが楽譜を真っ黒にしています。
非クラシックの楽譜はそれに比べて真っ黒ではありませんので一見簡単そうに見えますが、実はリズムが難しくて苦労することが多い。見た目よりも難しいことを肝に銘じてください。
もし、真っ黒でリズムも難しそうな楽譜なら、相当難しいと思われます。
判断基準5:ジャズ・フュージョンは見た目よりも難しい
私の経験では、同じ難易度に分類されていてもジャズ・フュージョンのほうが難しいことが多くありました。
ジャズやフュージョンも、楽譜の見た目よりも難しい
理由としては、
・Swing(スウィング)という、跳ねて弾くリズムのことが多い。このノリが難しい!
・テンションという難しい音が入ったコード(和音)が多用されているので、譜読みに時間がかかる。
ジャズに慣れていない方の場合、理解に時間がかかる。
・加えて前の項目と同様にリズムが難しいことが多い(特にフュージョン)。
・高速ジャズ・高速フュージョンも多い!
ですのでホント、ナメたらいかんぜよ、です(笑)
判断基準6:オクターブ奏、広範囲の移動が多用されている曲は難しい
これは、特に手が小さい方は必ず確認してください。
自分の手が、「オクターブは無理」なのか、「連続しなければ大丈夫」なのか、「1オクターブは大丈夫だけど、それ以上(9度や10度)は無理」なのかを確認してください。
範囲が広い高速のアルペジオも手が小さいと難しい場合があります。少しなら大丈夫だけど、ずっとだと手が疲れて弾けないという場合もあります。速度と量を確認してください。
最後に:1~6までを総合的に判断する
以上、1~5までを確認したうえで総合的に判断し、「大丈夫そう」「ちょっと頑張ったら弾けそう」「大変そうだけど将来弾けるようになりたい」「まず無理・・・(だけど楽譜買う)or(だから楽譜を買うのをやめる)」と判断してください。
私はこのやり方で楽譜を選んでいます。まあ弾けそうもない楽譜を買うこともありますが・・・^^;
以上、是非参考にしてくださいね!
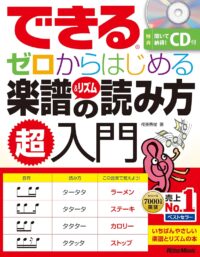
侘美秀俊先生の著書、おすすめです!
https://amzn.to/4mi0xvp